
2025年11月26日(水) 第1部 10:00~17:50
第1部 10:00~17:50
10:00~10:10 開会宣言
10:10~11:30 基調講演
科学的思考におけるモデル:説明、創造、そして概念工学へ
<概要>
この講演では、主に科学哲学の観点から、科学という営みの中心に位置するモデルの機能を考察します。
科学的思考や科学理論におけるモデルの特徴、モデルが科学史上において際立った役割を果たした例などを確認しながら、とりわけ重要なモデルの働きである科学的な説明と創造的な思考との橋渡しについて解説します。
最後に、モデルは概念とも深くかかわることから、現代哲学の新しい領域である概念工学についても簡単に触れたいと思います。
<登壇者>
東京大学大学院情報学環・学際情報学府 准教授
植原亮 氏

<プロフィール>
1978年埼玉県生まれ。
東京大学教養学部基礎科学科卒業、同大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。
関西大学総合情報学部教授等を経て、現職。
専攻は、自然主義哲学(科学哲学・分析哲学)、応用倫理学(脳神経倫理学・ロボット倫理学)など。
単著に『科学的思考入門』(講談社)、『遅考術』(ダイヤモンド社)、『思考力改善ドリル』『自然主義入門』『実在論と知識の自然化』(勁草書房)、共著に『人工知能とどうつきあうか』『脳神経倫理学の展望』(勁草書房)、『道徳の神経哲学』(新曜社)など。近著に『セルフコントロールの教室(仮)』(2026年早春刊行予定)。
理論的・概念的な研究だけではなく、執筆や教育などを通じた実践的な活動も行う。
11:30~11:40 休 憩
11:40~12:30 技術講演1
AI readyデータ整備のためのデータモデリング
<概要>
生成AIの普及は、仕事や暮らしへの影響だけでなく、職業観念や世の中の仕組みそのものをも根底から変えようとしています。AIの出力精度を高めるためには、AIが学習対象とするデータの品質が求められます。即ちデータマネジメントが必要とされています。
データマネジメントの基本は、「必要とするデータが何処にどんな形で存在しているのか」を明確にすることです。
そのための1つの解が、エンタープライズレベルのデータモデルの作成です。データモデルを作成することにより、重複して散在しているデータを認識し、概念・論理的に整理してビジネスの実態と照らし合わせて把握することができます。
データモデリングは古典的な手法ですが、AIの時代にもなお要請されている背景と実践的な手法をお伝えします。
<登壇者>
株式会社データアーキテクト 代表取締役
真野 正 氏

<プロフィール>
株式会社シーエーシーにて、製薬・飲料メーカー・航空会社・物流会社等の産業系のシステム設計・構築でDB設計・構築を中心に従事した後、情報資源管理(IRM)やデータモデリングコンサルティングに従事。 (22年間勤務)
2005年にデータアーキテクトとして独立し、データマネジメント、データモデリング、DB設計を中核としたエンタープライズ系業務に従事。
代表的な著書である「実践的データモデリング入門」( 2003年発刊、23刷)は現在も読み継がれている。
Udemyで「ビジネス推進のためのデータモデリング入門」を開講している(3,300名ご受講)。
JDMC、DAMA、勉強宴会会員。
12:30~13:30 昼休み
13:30~14:20 技術講演2
生成AI時代のドメインモデリング ― OOPとFPを超えて
<概要>
Scott Wlaschinの『関数型ドメインモデリング』では、関数型プログラミングの発想を取り入れたドメインモデリング手法が紹介されています。従来のオブジェクト指向をベースとしたドメインモデリングと何が違うのか、具体例をもとにお話しします。
ドメインモデリングは本来コミュニケーションのツールであり、実装技法に左右されず、曖昧さなく仕様を表現して欲しいものです。そこで本講演では、OOPやFPの思考法は踏まえつつも、仕様を明確に表現しきるモデルとはどういうものであるかについて考察します。
これは生成AIとの協働を実現するにおいて極めて重要な意味を持ちます。曖昧さのない仕様記述は、AIがより正確にビジネス意図を理解し、適切なコードを生成するための基盤となります。
人間とAI、そして人間同士のコミュニケーションを円滑にする、新しいドメインモデリングの可能性を探ります。
<登壇者>
株式会社ウルフチーフ 代表取締役
川島 義隆 氏

<プロフィール>
SIerで20年にわたり、さまざまな業界・業種のプロジェクトに携わった経験を活かし、独立後は複数の現場でアーキテクトとして活動しています。
イミュータブルデータモデルを提唱し、データモデリングを通じて業務を深く理解する手法を探求してきました。
現在は、この知見をドメインモデリングと統合し、新たな理論体系としての体系化に取り組んでいます。
14:20~15:10 技術講演3
Excelデータ分析で学ぶディメンショナルモデリング~アジャイルデータモデリングへ向けて~
→MF2025 技術講演3 資料(外部リンク)
<概要>
データ分析に適したテーブル設計の手法としてディメンショナルモデリングがあります。
この講演では「Excelでのデータ分析」を題材にして、初学者の方々にディメンショナルモデリングの概要をご紹介できればと思います。
<登壇者>
株式会社風音屋 代表取締役
ゆずたそ(横山翔)氏

<プロフィール>
リクルートやメルカリ、AWSを経て風音屋(かざねや)を創業。
Googleが認定する技術エキスパート Google Developer Experts や東京大学 経済学研究科 金融教育研究センター 特任研究員などを担当してきた。
2025年10月より独立行政法人情報処理推進機構(IPA)にて情報処理技術者試験委員を兼任。
データ基盤構築やデータ分析について積極的に情報発信をしており、主な著書・訳書に『実践的データ基盤への処方箋』『データマネジメントが30分でわかる本』『アジャイルデータモデリング』がある。
15:10~15:30 休 憩
15:30~16:20 技術講演4
こんにちは!データモデリング
<概要>
AI時代とは、端的に言えば「個々人が欲しいアプリを手軽に作れる」時代であり、裏返すと「アプリの粗製乱造」時代の幕開けとも言えます。
これらのアプリは非IT人材がデータモデリング不在のまま思いつきで作成して利用に至り、その後の顛末が不安になる懸念もあります。
この講演では、「データモデリングにおけるハローワールドとは」という観点から、我々データモデラーがAI時代のアプリ開発を導く方法をお伝えいたします。
<登壇者>
エークリッパー・インク 代表
羽生 章洋 氏

<プロフィール>
1968年大阪生まれ
最近は非IT職の方がデジタル人材として活躍できるようになるための支援を中心に活動中。
業務フロー作成ツール「マジカ」や要件定義図法「IFDAM」の作者
著書:「こんにちは!要件定義1【情報活用とデータベース編】」「ビジネスデザイン」「はじめよう!要件定義」「はじめよう!プロセス設計」「はじめよう!システム設計」「楽々ERDレッスン」「すらすらと手が動くようになるSQL書き方ドリル」他
16:20~16:45 技術講演5
要件定義の中心にモデルを置きLLMが出力した要件に責任をもつ
<概要>
現在のLLMは、要求・要件・仕様を簡単に作成できるようになりました。
しかし、会社固有の状況を反映し、整合性の取れたビジネス系システムの要件定義に
AIを活用するには、3つの課題があります。
・適切なコンテキストをどう用意するか
・LLMの出力をどのように軌道修正するか
・LLMの出力をいかに理解するか
この3つの課題を克服することで、LLMの出力に責任を持てるようになります。
本セッションでは、これらの課題を克服するためのモデルの役割と、Agentに要件を
定義させる様子を実演します。
<登壇者>
株式会社バリューソース 代表取締役社長
神崎 善司 氏

<プロフィール>
SIerでシステム開発全般の経験を積み、1980年代後半からソフトウェアエンジニアリングに注力。
1990年に株式会社バリューソースを設立し、オブジェクト指向技術を中心としたコンサルティングに従事。
物流、製鉄、ERP、会計、人事、Webサービスなど多様な業界のプロジェクトを支援してきた。
モデルベースでの要件定義の経験を「モデルベース要件定義」「RDRA3.0ハンドブック」として書籍化。
現在はRDRA導入支援、要件定義支援、既存システムの可視化支援を行うとともに、AIを活用した要件定
義やRDRAのグラフィカル表示ツールの開発に取り組んでいる。
16:45〜17:10 技術講演6
モデリングと生成AIで築く安心の設計 ― メタモデルに基づく設計書自動生成 ―
<概要>
生成AIがコードを書く「Vibe Coding」は注目を集めています。しかし社会インフラを支えるシステム開発では、より堅牢で安心な方法が求められます。本講演では、設計メタモデルを基盤に、生成AIを使って上流設計書から下流設計書を自動生成するプロトタイプを紹介します。WebUIによる逐次生成とAIエージェントによる生成をデモで示し、従来の開発スタイルを進化させながら生成AIを最大限活用する新たな道筋を考えます。
<登壇者>
株式会社東芝
フェロー 前田 尚人 氏、スペシャリスト 鈴木 昴裕 氏

<プロフィール>
株式会社 東芝 総合研究所 デジタルイノベーション技術センター 開発環境技術部
前田 尚人 フェロー
事業部での多様なシステム開発経験を活かし、開発管理支援環境(Redmine/GitLab/独自ツールなど)の研究開発と全社展開を推進。社内における開発環境の第一人者として、生成AI活用や技術標準化を通じて、開発現場の変革に取り組む。

鈴木昴裕 スペシャリスト
システム開発におけるツール活用の推進を担当し、設計工程の効率化と品質向上を目的とした技術の開発と展開を推進。
特に、設計メタモデルを取り入れた支援ツールの開発や、生成AIを活用した設計書自動生成のプロトタイプ構築に注力。
社内普及展開活動を通じて、現場の課題に即した実践的な改善を支援している。
17:10〜17:20 休 憩
17:20〜17:40 ワークショップ開催報告
ワークショップ①
モデル駆動設計をやってみよう(モデルをプログラミング言語で表現する体験学習)

<登壇者>
株式会社ビープラウド 代表取締役社長
佐藤 治夫 氏
ワークショップ②
「モデルとはモデリングとは何か」を本質観取しモデリングするワークショップ
~すべての知的活動はモデリングか?リベラルアーツとしてのモデリングに向けて~

<登壇者>
豆蔵デジタルHDグループCTO/IPA主任研究員/UMTPモデリング・アンバサダー
羽生田 栄一 氏
17:40〜17:50 休 憩
第2部 (18:10~19:45)
18:10〜19:40 パネルディスカッション
シン・UMTP宣言
モデリングネイティブを育てるには? 「AI時代のシン・データモデリングとは?」

<司会>
豆蔵デジタルHDグループCTO/IPA主任研究員/UMTPモデリング・アンバサダー
羽生田 栄一 氏
<概要>
本日の講演者をパネラーに、「AI時代のシン・データモデリングとは?」をテーマにディスカッションして頂きます。
<パネラー>
真野 正 氏、川島 義隆 氏、風音屋ゆずたそ(横山 翔)氏、神崎 善司 氏
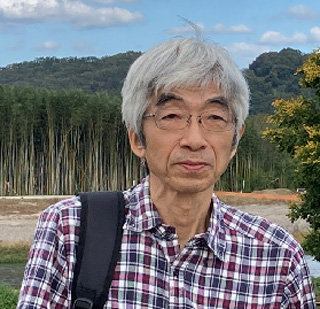


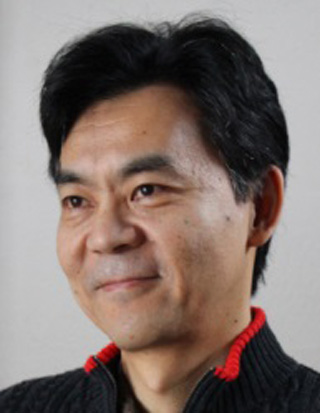
お問い合わせ先
→お問い合わせはこちらから
